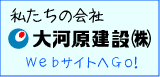去年の9月から5ヶ月間、この橋を見てきました。
静岡市清水区由比にある国道1号由比川橋。
下り線は昭和53年に築造されたコンクリート橋です。
 橋の長さは約120m。
橋の長さは約120m。
写真の左側は上り線で右側が下り線です。
写真は橋の下から撮影しています。
橋の右側に見える大きな管は工業用水の管路です。
 この場所から海をみるとこんな感じです。
この場所から海をみるとこんな感じです。
向こうに見えるのは東名高速道路の橋です。
光っているのは駿河湾。
国道から海までは50mほどです。
大きな台風が直撃すると通行止めになるところです。
 山のほうをみるとこんな感じです。
山のほうをみるとこんな感じです。
東海道線を走る貨物列車が見えます。
日本の交通の要衝といってよいでしょう。
昨日書きましたが由比川橋は劣化が激しく、その劣化にはいくつかの種類があります。
まず、見てすぐわかるのがコンクリートのひび割れ、浮き、はがれ、鉄筋の露出です。
実際の由比川橋の状況を見てみましょう。

これがコンクリートがひび割れているところです。
コンクリートが浮き上がり、叩けば落下する部分もあります。
 これは浮いたコンクリートが剥がれ落ち、鉄筋が露出しているところです。
これは浮いたコンクリートが剥がれ落ち、鉄筋が露出しているところです。
露出した鉄筋はすでに錆びています。

この写真はコンクリートのひび割れから染み出たコンクリート中の水酸化カルシウムが空気中の二酸化炭素と結合してできた炭酸カルシウムの結晶で遊離石灰と呼ばれます。
遊離石灰のあるところにはひび割れがあると考えられます。
ひび割れなどの劣化の原因はいろいろあります。
その原因を並べてみると・・・、
塩害(塩水や凍結防止剤の影響)
コンクリートの中性化(二酸化炭素などのガスの影響)
アルカリ骨材反応(骨材とはコンクリートの中に使っている石のことで、その性質による影響)
凍害(コンクリートが凍ってしまったときの影響)
疲労破壊(橋の上を走る大型車両などから繰り返し力を受けた場合のその影響)
PC鋼材等の劣化(PC鋼材とはコンクリートの中にある鋼材でコンクリートが受ける力を軽減する方向に力を発揮する鋼材で、その腐食による影響)
基礎の不同沈下(いくつかの基礎が沈下したとき、その沈下の大きさがそれぞれ異なった場合の影響)
水和熱による膨張や乾燥収縮(コンクリートが固まるときに発生する熱や、中の水分がなくなるときのコンクリート自体の膨張や収縮による影響)
化学的腐食(下水などに含まれる化学物質による影響)
火害(コンクリートのそばで大規模な火災があった場合の高熱による影響)
とても覚えきれないので参考書から写しました。
ほんとにたくさんあるんです。
由比川橋の場合、この原因のなかでも塩害によるものが一番影響していると想像できます。
それはこの橋がとても海に近いからです。
もし近所の橋の近くを歩くことがあれば、少し目を凝らしてコンクリートの表面を見てみてください。
何かしら劣化しているところが見つかるかもしれません。
表の顔、道路から見た橋梁は便利で頼もしく、とても頑丈にみえるでしょう。
しかしその下、裏の顔をみたら実はもうしわだらけの老人になっているかもしれません。
私はこういった劣化は時間が止まらない限り永遠に続くものだと思うのです。
やっぱり道路は生きているんだなと、ひとり感じ入ってしまうのです。
次回は由比川橋を直す方法、補修の方法について書きます。


 畳にはどうも縁が深いようです。
畳にはどうも縁が深いようです。